第3章 資本の循環
(1)資本とは何か?
資本論を読み進んでいるうちに、ふと気になり、分からなくなってしまったことがある。それは、資本論の「資本とは何か?」という問題である。これは自明のようでありながらあらためて考えると、その実体・定義はどこにも明かされていないのである。
①現金のことか
②預金も含めたものを言うのか
③借り入れた場合の現金はどうなのか
④株式会社で言う資本金のことか
⑤個人企業の場合は何を指すのか
⑥俗に言う資本家との関連性はないのか、等々。
私の考えはどこまでも広がってきりがなく、頭はすっかり混乱してしまったのである。
この時思い付いたのが会計理論である。資本論は資本主義社会の経済構造を解明したものであり、会計理論は、その資本主義社会で現実に適用されている理論ではないか。とすれば両者には何らかの共通点、最大公約数的なものがあってしかるべきであろう。そう思って探していると、資本論の「資本とは何か?」を理解するのに十分なヒントを与えてくれる書に巡り会うことができた。それは、これから紹介する「近代会計理論」(山桝忠恕、慶応大学教授著)である。紹介が長くなるので、これによって私が言いたいことの結論を先に述べておこう。
その第1は、資本論で言う「資本」とは、様々な態様を持っており、時々刻々と変化するものである。資本論に曰わく「資本は貨幣形態をとったり、商品形態をとったりしながら自己増殖する」(第1巻P.169、趣意)と。従って、資本論とは、「資本主義社会における企業資本の運動を論じたもの」ということができる。
そして第2は、「資本の運動論」ということであれば、会計理論こそ、まさしく資本の運動を計数的に把握する理論である。従って、その精密な思考方法をもって資本論を精査すれば、論理の展開に無理がなかったか、飛躍がないかを知ることが可能であろう。
以上の2点である。
(2)資本論における「企業資本運動」のとらえ方
さっそく「近代会計理論」の紹介を始めよう。この書で山桝氏は、会計理論の説明に入る前に、一般的な企業資本運動について述べている。これは資本論における企業資本運動のとらえ方そのものである。
「いうまでもなく、企業は資本主義経済社会に特有な事業経営形態である。直接には資本の自己増殖ないし利潤の追求を行動目標とする経営体であるというところに、その特色を持つ。そして、そのような企業の経済活動は、なるほどこれをその展開する具体的な活動に即してながめるときには、生産に必要な資材の購入、労働力の確保、製品ないし用役の生産、さらにその販売などのかたちをもってわれわれの目に映じる。しかし、ひとたびそれらの諸活動を統一的・理念的な立場においてとらえようとするならば、それらを一定の目的によって導かれた企業資本の統一的な運動として把握しなければならない。一見したところでは千差万別であるにしても、企業における経済活動は、本質的には企業資本の機能活動の反映であり、まさに資本の自己増殖活動自体の具体的な表現形態に他ならないからである。」(近代会計理論P.6)
山桝教授は、まず企業における経済活動の特色を説明することから入られている。次に資本論における企業資本の運動を説明するところに入るので紹介を続けよう。
「もともと、そのような企業資本の運動は、企業の具体的な活動を可能とし利潤の獲得の原資ともなる貨幣の流入をもって始まる。そして、このようにして主として貨幣のかたちでもって企業内に流れ込むに至った資本というのは、一定の計画のもとにつぎつぎと放射され、資本としての力を思いのままに発揮せしめられることとなる。たとえば、それらの一部は、原材料・機械・設備などにあてられることによって生産資本として機能し、またその一部は商品資本にも転態する。そして、業績が順調に推移するかぎりは、さらにこれがふたたび貨幣資本に転態することによって、ここにその自己増殖の達成を見るに至るわけである。つまり、この企業資本運動は、
Pm
G───W { ………(P) ………W’─── G’
A
という形式をもって、しばしばその解説が行われているように、資本としての貨幣(G)の生産手段および労働力への転態、それらの内部移動、生産された商品(W’)の貨幣 (G’)への転態という行程をたどりつつ、しかもそれらの果てしなき循環を繰り返しているものと言える。」(同P.7)
ここに出てきた
Pm
G───W{ ………(P)………W’───G’
A
こそ、資本論第2巻第1章「資本の姿態変換とその循環」に出てくる再生産表式である。続いて、この後に述べられた部分に注目していただきたい。
「ただ、そのような企業資本の運動過程というのは、これをその階梯に即して、計数的にも逐一捕捉していかなければ、その充分な管理を期しえないこと、いうまでもない。そしてそのことが、おのずから企業会計という職能の台頭を促したものと言えよう。」(同P.7)
つまり、企業資本をきちんと管理するために、企業会計なるものが発展してきたというのである。現時点における会計理論が、完璧であるとは言えないまでも、計数管理という面においては、これ以上の理論はあるまい。
(3)企業資本運動の態様
それでは、企業会計における「企業資本の運動」はどのようにとらえられているであろうか。
①資本の調達分
「そこで、企業資本の演じる目的活動の態様を、いま少しく具体的に跡づけると共に、その企業会計的な観点よりする取り上げかたを概観してみよう。
すでに指摘したように、企業資本の運動は、多くの場合、資本としての貨幣の流入をもって始まる。そして、それら資本導入の原初的な形態というのは、いわゆる外部からの新規調達、すなわち俗にいう資本の元入れないしは借り受けに他ならない。発足後はそれらの循環運動が順調に推移していく限り、自己増殖的な調達、つまり生産ないしは販売に基づく稼得、ひいてはそれら稼得されたものの社内留保による補強・充実もまた可能である。そしてそれらもまた、漸次、循環運動に加わっていくはずである。したがって、この資本の入手には、けっきょくのところ、二つの形態のものがあり得る。ここでは、前者を仮に資本の算段分、後者を仮に資本の培養分とでも呼んでおこう。そして以上のことを整理すれば、次のようになる。」(同P.12)
[資本の調達分]
1, 資本の算段分(払込資本および負債)
2, 資本の培養分
イ、 資本の蓄積分(留保利益)
ロ、 資本の稼得分(収 益)
こうして、山桝教授は、企業資本の態様を具体的に跡づけることによって、私が最初に提起した疑問、即ち「資本とは何か」という問いに少しずつ回答を示してくれているのである。紹介を進めよう。
②資本の行使分
「ところで、このようにして企業内に流れ込むに至る資本というのは、これもすでに明らかなように、一定の計画に基づいて次々に生産資本なり商品資本なりに転態していくわけである。それらの部分を、仮に資本の活用分と呼んでおこう。そしてこの資本の活用というのは、とりもなおさず原価(cost, Kosten)の生起を意味する。ただ生産資本ないしは商品資本に転態した企業資本というのも、しょせんは資本としての循環運動の過程に位しつつある存在に他ならない。
従って、どの時点でそれらを観察してみても、常にそこには、自己増殖のための犠牲となってその価値を他にゆだね、自らとしては、一応解消するに至っている部分と、まだその段階にまでは達していない部分とがありえよう。そこで、仮に前者を資本の費消分、後者を資本の充用分と呼んでおくが、両者の区別は、もともと本質的なものではない。
次に、資本の中には、外部に出向中のものもないわけではない。そして、それらは、それ自体としては少なくとも直接的には損益に関係のない、いわば中性的なものであるとも言える。ここでは、それらを仮に資本の派遣分ないしは派出分とでも呼んでおくことにする。そこで、以上のことを整理すれば、次のようになる。」(同P.13)
[資本の行使分]
1, 資本の活用分
イ、 資本の費消分(費用)
ロ 、資本の充用分(費用性資産)
2, 資本の派出分(投資および債権)
「近代会計理論」では、以上の説明の後で更に捕捉されている点がいくつかある。しかしここでは、会計理論の概要が理解されれば目的を達するので、それらは省略して次へ進もう。
③ 資本の待機分
「さて、われわれは、資本の動きを、便宜その調達から行使へとたどってみたわけであるが、資本の中には、たえず貨幣資本そのものとして温存されつつ、いずれは早晩訪れるであろうところの、それが用立てられる機会を待っている部分というのもあったわけである。したがって、調達をみた資本の額と行使にあてられた資本の額とのあいだには、おのずから若干の差がみられ、そこには、
資本の行使分の額+資本の待機分の額=資本の調達分の額
という関係こそが成立する。そして、企業会計にあっては、このような、資本の調達分の額と、資本の待機分の額ならびに行使分の額とのあいだに、もともと存在しているはずの均衡関係に即しつつ、企業資本の構成のうえに現れる具体的な変動が明らかにされる。と共に、それを通じて企業資本の有り高とその増減との計算が、きわめて有機的・組織的に行われているわけである。」(同P.14)
以上が「企業資本運動の態様」である。次は、この企業資本の運動を、企業会計ではどのように捉えていくのか、という部分に進もう。会計理論をある程度理解している人にとっては、企業資本の運動が如何なるものであるかということが、更に明確になってくるであろう。
(4)企業会計における企業資本運動のとらえ方
① 企業資本運動の図解
「企業会計が企業資本の運動を計数の側面から統一的に捕捉しようとするものであることは、しばしば述べた。しかし、かんじんの企業資本の運動は、もともと無限持続的なものであって、ついにその終わりをみることがないものと思わねばなるまい。しかし企業としては、経営上の諸種の指標を得るうえからも、そしてまた、資本の提供者に対して報告や分配を行ううえからも、むしろある時期ごとに、企業資本の構成がどうなっているかということと、企業資本の増殖高がどれくらいに達しているかということとを、いわば経常的、反復的に確かめてみる必要がある。
そこに、おのずから、会計期間ないしは会計年度の概念が生まれ、そのように元来は切れ目というもののない資本の動きを人為的に区切って、すべての勘定単位を締め切り、それら一定期間の記録・計算に整理を施しつつ資本構成の判定と資本増殖額の算定とを試みることとなる。これが俗に決算と呼ばれている会計行為にほかならない。
そこで、今、日頃の記録・計算の顛末を一時点において総括のうえ、企業資本自体の計算を試みるとして、これを図解するならば、それは、たとえば、次の図のようになることであろう。」(同P.15)
この図は、とりもなおさず「(3)企業資本運動の態様」として先に紹介したものの図解である。
② 損益計算書
次に、この図から、損益計算書と貸借対照表が導き出されるところを紹介しよう。
「上図にあって、借方の一部に含められている費消分というのは資本犠牲を意味し、実は資本としてはすでに解消してしまっているわけである。ただ、それらの費消分は、あながち無意味もしくは一方的に解消し去ってしまったというわけのものではない。むしろこの犠牲によって、それに代わる新しい資本の稼得が達成されているはずである。つまり、他方の稼得によって費消分の回収が行われ、費消よりも稼得のほうが上回るときには、そこにその差額だけの資本増殖さえもが成就しているわけである。したがって、この勘定図解の中から、次の図のように、費消分と稼得分とだけを取り出し、両者の額を対応させることによって、資本における正味の稼得分、すなわち増殖分の額の計算が可能になる。
なお、このように、資本の流入すなわち増加ではあっても、外部からの算段や過去の年度の蓄積によってその確保をみたものではなく、費消とのあいだに因果関係を保ちつつ、当会計年度において稼得されるに至った資本のことを、収益という。また稼得のために費消されることにより流出した資本のことを費用、そしてそれらの両者の差額、つまり、増殖分のことを利益ないしは利潤と呼んでいる。尤も、資本運動が、常にこのように増殖のみを結果するとばかりは断定できない。資本にむしろ収縮が生じつつあるという、いわば、その逆の場合もまた、ありうるからである。そのようなときに現れるマイナスの差額は、これを欠損という。
そこで、費消と稼得との対比を通じて企業資本の増殖状況いかんを示す先の勘定を、これらの専門用語をもって表現し直すならば、それは当然次の図のようになる。そして、これが実は、かの損益計算書の原型をなす。」(同P.16)
③ 貸借対照表
本章は、山桝教授著の「近代会計理論」から、その明解なる企業資本運動のとらえ方を紹介してきた。最後に、貸借対照表の導き出し方を紹介して終わりにしたい。
「ところで、このようにして確かめられた利益の額だけは、資本運動を経ることによって、結果的に企業資本がそれだけ増殖をみるに至っていることを物語る。つまり、それは調達資本の増加を意味すると共に、これに相応する額だけは、待機中の資本もしくは行使中の資本、あるいはそれら双方の額もまた、当然に増加していなければならない。
そこで今度は、先に掲げておいた企業資本勘定の図解の中から、すでに抜き出した費消分と稼得分とは別にして、その他の部分を取り上げてみよう。さきの仮想図解を前提にする限り、そこにあっては一見して明らかなように、稼得分の額の方が、費消分の額よりも多額である。同様に、待機分の額と、行使分の中の未費消分の額との合計額が、外来の調達分と過去の年度の蓄積分との合計額よりも多い。しかもその差額は、他方で算出した増殖分の額に、おのずから合致するという関係がみられる。そしてそのことは、資本運動の進行につれて、資本の費消を上回る稼得の故に、いわば内面的に新資本が確保され、ちょうどその分だけは借方側も必然的に増強されていることを如実に物語っているわけである。
したがって、既掲の勘定図解から費消分と稼得分とを除くと共に、借方と貸方とがバランスを保ちうるように、貸方側に差額を計上しさえすればそこに成立をみる勘定には、結局のところ資本運動の結果としての資本残高だけが総括されることになる。そしてそれらが相寄って一時点における企業資本の構成を描写すると共に、実はそこでもまた、残高の比較という方法を通してであるが、やはり資本の増殖分すなわち利益の額の計算が行われていることになる。
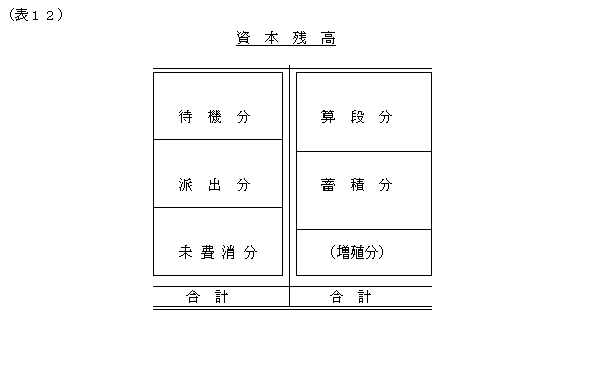
なお、企業会計上では、資本の待機分のことを貨幣性資産、未費消分を費用性資産、外部に派出中のものを債権および投資、これらを広く総括して資産と呼ぶ。また、調達分のうち外部からの算段分というのは、企業会計上の表現を用いるならば、その源泉のいかんによって、負債と払込資本とに大別されよう。なお、前会計年度の利益の中で分配されずに内部に留保されている分、すなわち蓄積分については、さしあたりのところ、それを留保利益と呼んでおく。
そこで、一時点における企業資本の残高すなわち有高の構成と共にそれを通じて企業資本の増殖状況いかんをも示す先の勘定を、これら企業会計上の用語をもって表現し直すならば、それは、次図のようになる。そしてこれこそが、貸借対照表の原型をなす。」(同P.17)
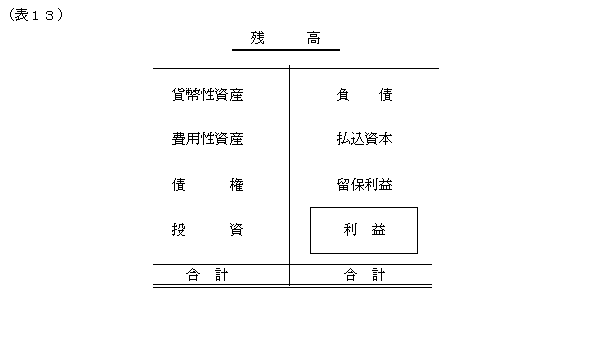
(5)資本の循環と回収理論
以上で、「近代会計理論」からの紹介を終わるが、ここでもう一度、企業資本運動の図解をみていただきたい。全体をマクロ的に観察すれば企業資本が次の図のように左回りに動いていることに気付かれると思う。
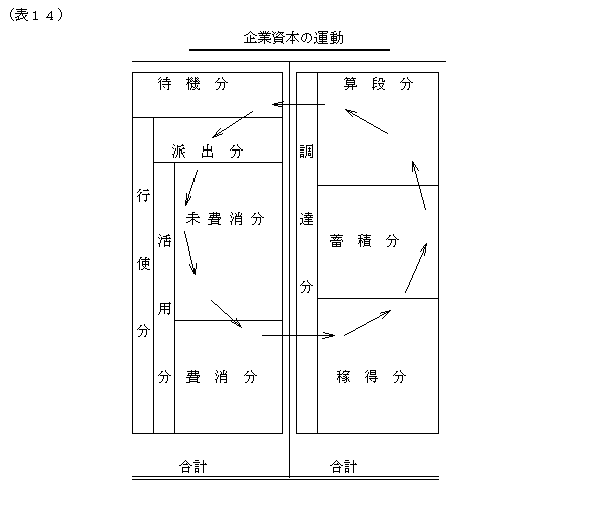
つまり、[ 算段 → 待機 → 行使 → 稼得 → 蓄積 → 算段 ]という具合に、ゆっくり或いは速く変化していることがわかるのである。
このことを、鹿児島県立短期大学講師の阪本寅蔵氏は、非営利会計の「消費理論」に対して、企業会計の「回収理論」として説明されているので紹介しておきたい。
「回収するにはまず消費が先行しなければ不可能である。この場合の消費はあらかじめ投資された資産を前提としている。この条件に従えば勢いつぎのような運動形態をとる。
負債・資本 → 資産 → 費用 → 収益 → 負債・資本
( 投 資 ) (消費) (回収) (投 資)
という下図のような左回りの旋回運動を行って、利益を加えその運動は毎期大きな弧を描いてゆく、それは左回り、螺旋状循環運動である。有形固定資産が減価償却の手段で費用化する左旋回運動と同一方向であり、したがってこの減価償却の運動を巻き込んでいって矛盾はない。」(「非営利会計」P.152)
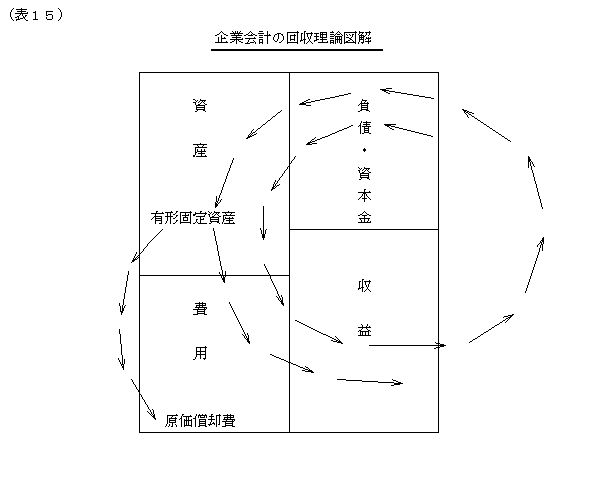
ここで、資本論で展開される資本の循環(再生産表式)と企業会計の回収理論とを対比すれば、次のことが理解できる。
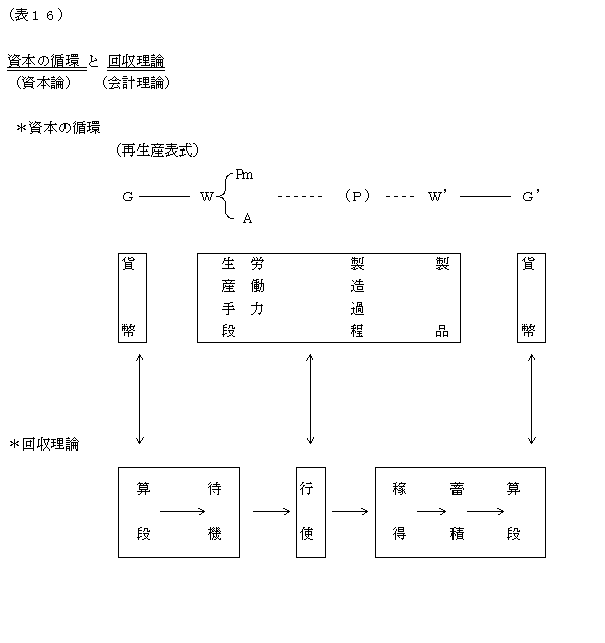
①再生産表式のGは、回収理論の待機分に相当する。
②再生産表式の、
Pm
W{ ………(P)……… W’
A
は、回収理論の行使分に相当する。この部分は、再生産表式が、
Pm
W{ ………(P)……… W’
A
と詳しい割に、回収理論の方が「行使分」という短い一言で相当させているように見える。しかし、この「行使分」を展開すれば、次の図でも明らかなように、派出分+活用分(未費消分+費消分)となる。更に費消分を展開すれば、財務諸表の付属明細書であるところの、「製造原価報告書」の内容にまで広がりを持っているのである。
Pm
W{ ………(P)……… W’
A
は、行使分の中の一部分である製造原価報告書の内容に相当すると言えよう。
③再生産表式の、W’-G’は、回収理論の稼得分、蓄積分に相当する。
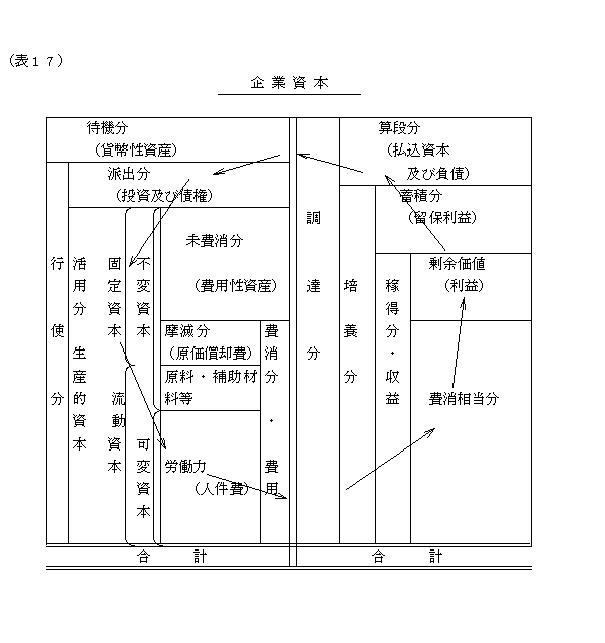
マルクスの再生産表式は価値次元において構成され、すぐれて抽象的な理論であるから、これを価格次元の現実分析に利用することは否定されるべきだという考え方は、わが国のマルクス経済学者のあいだではかなり根強く存在しているようである。
しかし、資本論にも、「以下の研究のためには生産価格と価値との相違は無視しても良い。というのは、ここで考察するように、労働の年間総生産物の価値、つまり社会的総資本の生産物の価値を考察する場合には、およそこのような相違はなくなってしまうからである。」(第3巻P.840)とあり、
また「資本主義的生産様式が解消した後にも、社会的生産が保持される限り、………簿記が以前よりもいっそう重要になる………」(第3巻P.859)とある。
これに勇気を得て本章では、価値次元の再生産表式と、価格次元の会計理論とを同次元において論じていることを了解願いたい。
本章は、主として資本論第2巻に相当する部分を、会計理論と対比させつつ論じてみた。そして、ここで明確にしたかったのは次の2点である。
第1に、資本論でいう資本とは何か、ということ。
第2に、企業資本の同じ活用分でも、未費消分と費消分とでは、その性格が全く異なるということ。つまり、前者は貸借対照表項目(stock)であり、後者は損益計算書項目(flow)であるということであった。
これらを明確にしたことは次章において二つの法則、なかんずく、第二法則の検討をする際にその効果を発揮するであろう。
第2章「資本論の基本命題」が資本論の縦の柱を論じたのに対し、本章「資本の循環」は、資本論の横の柱(梁)について論じたということができる。設計図に例えれば、剰余価値の生産・資本の蓄積・利潤への転化等を論じた資本論第1巻及び第3巻は、立面図であり、資本の循環と回転等について論じた第2巻は、平面図であると言うこともできよう。