戞係復丂丂俀偮偺朄懃偺専摙
丂
乮侾乯戞侾朄懃乮亖婎杮柦戣噦 俆乯偺専摙
乽徚旓偝傟傞惗嶻庤抜偺壙抣丄偡側傢偪晄曄帒杮晹暘偩偗傪戙昞偡傞壙奿梫慺偺憡懳揑側戝偒偝偼丄拁愊偺恑揥偵惓斾椺偡傞偱偁傠偆偟丄懠曽偺丄楯摥偺戙壙傪巟暐偆壙奿梫慺丄偡側傢偪壜曄帒杮晹暘傪戙昞偡傞壙奿梫慺偺憡懳揑側戝偒偝偼丄堦斒偵丄拁愊偺恑揥偵斀斾椺偡傞偱偁傠偆丅乿乮戞侾姫俹.651乯
丂偙傟偑乽帒杮庡媊揑拁愊偺堦斒朄懃乿乮偙偙偱偄偆戞侾朄懃乯傪帵偡暥偱偁傞丅偙傟偐傜偙偺戞侾朄懃偺専摙偵擖傞偑丄傑偢僀僊儕僗偺嵟嬤偺宱嵪忬嫷傪徯夘偡傞偙偲偐傜巒傔傛偆丅
丂乽奒媺摤憟偺憡懳揑側桪埵偼楯巊偺偁偄偩傪峴偒棃偟偨偗傟偳傕丄慡懱偲偟偰傒傟偽丄楯摥幰奒媺偺椡偺惉挿偑戝偒偔嶻嬈偺廂塿惈乮亖棙弫暘攝棪乯傪尭彮偣偟傔偨丅乿乮乽捓忋偘偲帒杮庡媊偺婋婡乿俹.37乯
丂乽1964擭偐傜1970擭傑偱偺偁偄偩偵丄棙弫暘攝棪偼丄傎偲傫偳敿尭偟偨丅拝幚側壓崀悥惃偼丄50擭戙偺弶傔埲棃懚嵼偟偰偄偨丅偡側傢偪丄暘攝棪偼丄1950乣1954擭偺丄25.2僷亅僙儞僩偐傜1960乣1964擭偺21.0僷亅僙儞僩偵掅壓偟偨丅偩偑丄偦傟埲崀丄拝幚側掅壓偼愥曵偵揮壔偟偨丅棙弫暘攝棪偼1964擭偺21.2僷亅僙儞僩偐傜1970擭偺丄12.1僷亅僙儞僩偵掅壓偟偨丅乿乮摨俹.61乯
丂
丂 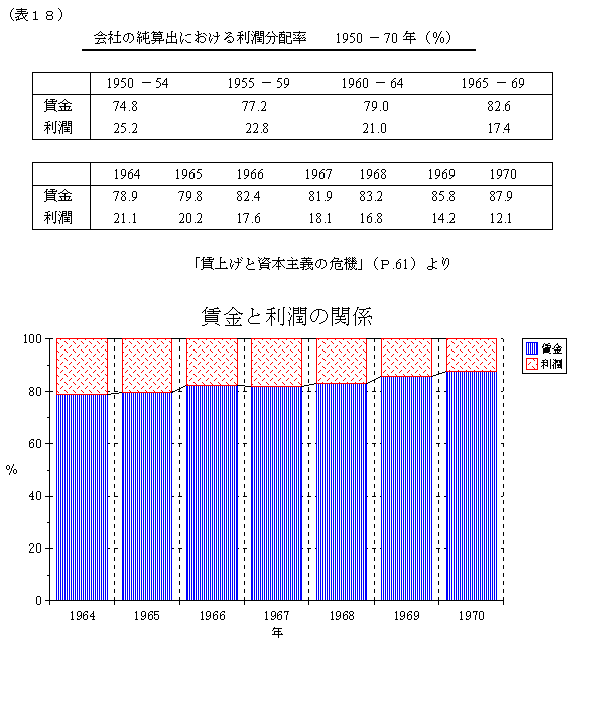
丂
丂乽傕偟傕帒杮壠偑僐僗僩乮捓嬥乯偺忋徃傪壙奿偺堷偒忋偘偵傛偭偰杽傔崌傢偣傞偙偲偑偱偒傟偽丄斵傜偺棙弫儅乕僕儞傪彎偮偗側偔偰偡傓偩傠偆丅偩偑丄傕偟斵傜偑巗応傪幐偭偰偼側傜側偄偲偡傟偽丄偨偩懠崙偺嫞憟婇嬈偑壙奿傪忋偘傞掱搙傑偱偟偐丄偦偺壙奿傪忋偘傞偙偲偼偱偒側偄丅乿乮摨俹.68乯
丂乽棙弫暘攝棪偺掅壓偺婎杮揑棟桼偼丄堦曽偵偍偗傞壿暭捓嬥偺忋徃偲丄懠曽偵偍偗傞崙嵺嫞憟偺椵恑揑寖壔偲偺偁偄偩偱偺棙弫儅亅僕儞偺埑弅偵偁傝丄宱嵪揑掆懾偼丄憡懳揑偵傎偲傫偳偦傟偲娭學偑側偄丅乿乮摨俹.69乯
丂
丂乽僨亅僞偑晄廫暘偩偐傜棙弫暘攝棪傪惓妋偵斾妑偡傞偙偲偼崲擄偩偗傟偳傕丄奺崙偺偙偺弴埵偼傎偲傫偳傄偭偨傝偲廂塿惈偺弴埵偵堦抳偟偰偄傞丅擔杮偼抐慠嵟崅偺棙弫暘攝棪傪帵偟偰偍傝丄EEC彅崙偼偦傟傛傝掅偔丄偦偟偰僀僊儕僗偲崌廜崙偼慡懱偺偆偪偱嵟掅偱偁傞丅1950擭戙偵崅偄棙弫暘攝棪偺堐帩傪嵟傕傛偔側偟偊偨嶰偮偺崙亅亅亅擔杮丒僀僞儕傾丒僪僀僣亅亅亅偑丄愴慜愴拞偵僼傾僔僗僩惌尃偺巟攝壓偵偁偭偨彅崙偱偁傞偙偲偼丄報徾揑偱偁傞丅
偙傟傜偺崙偺撈棫偟偨楯摥塣摦偺夡柵偼丄帒杮偑愴屻婜偵丄楯摥塣摦偑夞暅偱偒傞慜偵丄偒傢傔偰崅偄棙弫暘攝棪傪偍偟偮偗傞偙偲傪壜擻偵偟偨丅楯摥塣摦偑嵟傕媫懍偵嵞寶偝傟偨僀僞儕傾偱丄宱嵪揑婏愓偼嵟弶偵廔傢偭偨丅楯摥塣摦偑帩懕揑偵嵟傕庛偐偭偨擔杮偱偼丄宱嵪揑婏愓偼嵟傕挿偔帩懕偟偨丅乿乮摨俹.109乯
丂
丂埲忋偺儗億亅僩偐傜尵偊傞偙偲偼丄嵟嬤偺僀僊儕僗宱嵪偺幚忬偼丄楯摥塣摦偵傛傞楯摥幰奒媺偺惉挿偵傛偭偰丄偮傑傝丄捓嬥偺忋徃偵傛偭偰棙弫偑壓崀偟偰偒偨丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偙偵偼俀偮偺廳梫側帠幚偑娷傑傟偰偄傞丅
偦偺侾偮偼丄乽楯摥幰奒媺偺惉挿偵敽偆捓嬥偺忋徃乿偲偄偆揰偱偁傝丄偙傟偼丄儅儖僋僗偺梊應偲偼慡偔媡偺寢壥偱偁傞丅儅儖僋僗偼丄帒杮庡媊幮夛偵偍偗傞楯摥幰奒媺偺媷朢壔傪抐尵偟丄梊應偟偨偑丄楯摥幰奒媺偺惉挿偲丄偦傟偵敽偆捓嬥偺忋徃側偳偼柌憐偩偵偟側偐偭偨偺偱偁傞丅
偦偟偰懠偺侾偮偼丄乽捓嬥偺忋徃偵敽偆棙弫偺壓崀乿偲偄偆揰偱偁傞丅偙偺帠幚偼捓嬥偲棙弫偲偑丄憡懳棫偡傞娭學偵偁傞偙偲傪徹柧偟偨偲尵偭偰傛偄偱偁傠偆丅懄偪丄壜曄帒杮偺憹戝偼丄忚梋壙抣偺尭彮傪堄枴偟丄媡偵丄壜曄帒杮偺尭彮偼丄忚梋壙抣偺憹戝傪堄枴偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅
丂偟偐偟乽忚梋壙抣偼壜曄帒杮偐傜惗傑傟丄晄曄帒杮偐傜偼惗傑傟側偄乿偲偄偆婎杮柦戣噦俁偺嘇偐傜偡傟偽丄壜曄帒杮乮捓嬥乯偲忚梋壙抣乮棙弫乯偲偺娫偵偼丄偨偲偊忚梋壙抣棪偵庒姳偺曄摦偑偁傠偆偲傕丄偦傟傜偺憹尭忬嫷偵憡娭娭學偑偁傞偼偢偱偁傠偆丅
懄偪丄壜曄帒杮偺憹戝偼忚梋壙抣偺憹戝傪堄枴偟丄壜曄帒杮偺尭彮偼忚梋壙抣偺尭彮傪堄枴偡傞摍偺娭學偱偁傞丅摦偐偟擄偄僀僊儕僗偵偍偗傞摑寁忋偺悢帤偼丄椻崜偵傕帒杮榑偵偍偗傞婎杮柦戣噦俁偺嘇偑岆傝偱偁傞偙偲傪徹柧偟偰偄傞丅
丂偝傜偵丄摨偠摑寁忋偺悢帤偼丄戞堦朄懃乮亖婎杮柦戣噦俆乯傪傕丄岆傝偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅懄偪丄儅儖僋僗偼乽晄曄帒杮偺憡懳揑憹戝偲丄壜曄帒杮偺憡懳揑尭彮乿偵傛傝楯摥幰偑媷朢壔偟丄傗偑偰廂扗幰乮帒杮壠乯偑廂扗偝傟傞偱偁傠偆偲梊應偟偨丅偟偐偟丄楌巎揑帠幚偼丄傓偟傠媡偺僐亅僗傪偨偳偭偰偄傞傛偆偱偁傞丅
偮傑傝丄乽壜曄帒杮乮恖審旓乯偺憡懳揑憹戝偲忚梋壙抣乮棙弫乯偺憡懳揑尭彮乿偵傛偭偰丄帒杮壠乮婇嬈乯偑媷朢壔偟丄傗偑偰帒杮庡媊宱嵪偼曵夡偡傞偱偁傠偆丄偲丅晄曄帒杮丄壜曄帒杮丄忚梋壙抣偺憹尭忬嫷傪丄儅儖僋僗偺梊應偲僀僊儕僗偺摑寁偑帵偡帠幚偵懄偟偰恾帵偡傟偽丄戝巪師偺傛偆偵側傠偆丅
丂
丂 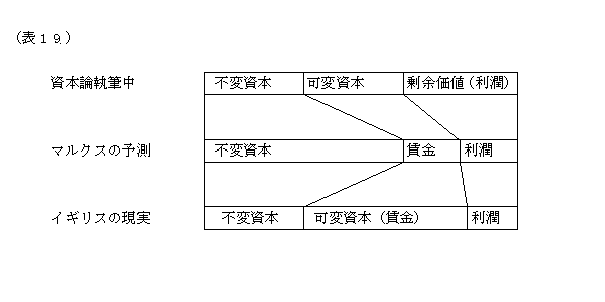
丂 丂
丂崱丄婎杮柦戣噦俁偺嘇偺柕弬傪巜揈偟偨偮偄偱偵婎杮柦戣噦俁偺嘆偺柕弬偵傕尵媦偟偰偍偒偨偄丅嶄壆懢堦挊乽孮壔偺峔恾乿乮俹.283乣4乯偵傛傟偽丄
丂乽崱擔乮1980擭乯偺擔杮偼丄傕偼傗岺嬈幮夛偱偼側偄偟丄傑偡傑偡側偔側傝偮偮偁傞偲偄偆帠幚偩丅崱傗悽奅偺愭恑彅崙偱偼丄戞嶰師嶻嬈偺廇嬈幰偑夁敿悢傪愯傔偰偄傞丅
擔杮偱傕慡廇嬈幰偺偆偪戞嶰師嶻嬈偺愯傔傞斾棪偑丄53僷乕僙儞僩偵払偟丄戞擇師嶻嬈偺34.9僷乕僙儞僩傪戝偒偔忋夞偭偨丅偟偐傕戞擇師嶻嬈廇嬈幰偵摑寁偝傟偰偄傞拞偵偼丄惢憿嬈偺婇嬈偱塩嬈娭學傗挷嵏丄峀曬丄嬥梈側偳戞嶰師嶻嬈揑側怑庬偵偨偢偝傢偭偰偄傞恖乆偑憡摉悢偄傞偐傜丄幚嵺偺悢偱偼丄戞嶰師嶻嬈娭學幰偺斾棪偼偙傟傛傝偼傞偐偵懡偄偲傒偰傕傛偄偩傠偆丅
丂偝傜偵嵟嬤偺廇嬈幰斾棪偱傕丄戞嶰師嶻嬈偺怢傃偼挊偟偔崅偄丅1970擭埲崀丄戞嶰師嶻嬈廇嬈幰偺斾棪偼俈僷乕僙儞僩傕憹偊偰偄傞偺偵丄戞擇師嶻嬈偺偦傟偼慡偔偺墶偽偄偩丅
丂偙偆偟偨孹岦偼丄廇嬈幰偽偐傝偱側偔丄搳帒妟偵偮偄偰傕惗嶻崅偵偍偄偰傕傒傜傟傞偲偙傠偱偁傞丅傑偨丄庒幰偨偪偺廇怑婓朷愭偲偟偰傕丄戞嶰師嶻嬈嬈庬偑抐慠懡偄丅惢憿嬈偺夛幮傪婓朷偡傞幰偱傕丄杮幮帠柋傗峀曬丄挷嵏側偳戞嶰師揑怑庬偵懳偡傞婓朷偑嫮偄丅丂埲忋偺傛偆偵丄戞嶰師嶻嬈偙偦偑丄尰嵼偺拞怱嶻嬈偱偁傝丄愭抂惉挿嶻嬈偱偁傝丄庒幰偨偪偺媮傔傞嶻嬈偱傕偁傞丅摉慠丄懡偔偺恖乆偑廧傒偨偑傞搒巗偼丄戞嶰師嶻嬈偺敪揥偟偨搒巗偩丅偦偟偰偦偺孹岦偼丄偙傟偐傜偺亀抦宐偺暥壔亁偺帪戙偵傑偡傑偡嫮傑傞偱偁傠偆丅乿偲偁傞丅
丂
丂 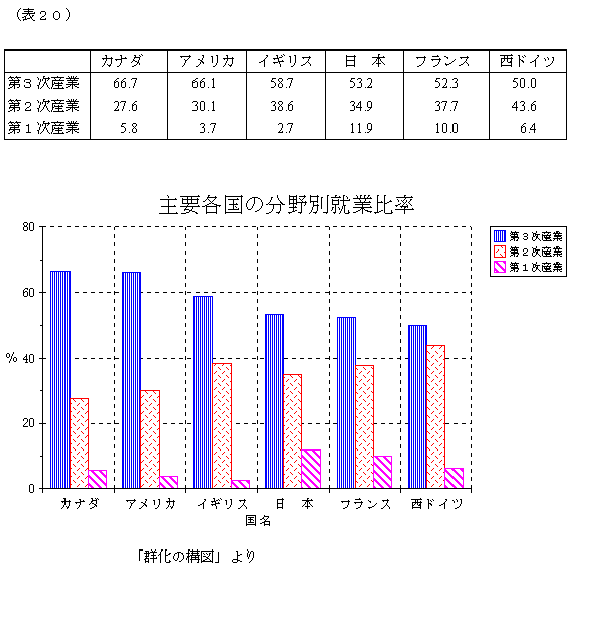
丂
丂 丂偙偺堷梡暥偲丄師偺柦戣偲傪斾傋偰梸偟偄丅乽忚梋壙抣偼惗嶻夁掱偱惗嶻偝傟丄棳捠夁掱偱偼惗嶻偝傟側偄乿乮婎杮柦戣噦俁偺嘆乯丅
丂帒杮榑偵傛傟偽丄乽彜嬈帒杮傕棙巕惗傒帒杮傕帒杮庡媊幮夛偱偼攈惗揑側宍懺偱偁傞乿乮戞侾姫俹.179乯丅偟偐偟丄崱傗丄偦偺攈惗揑宍懺偑慡嶻嬈偺夁敿悢傪愯傔傞偵帄偭偰偄傞偺偱偁傝丄偙傟傕儅儖僋僗偑梊憐偩偵偟側偐偭偨偙偲偱偁傠偆丅
丂峏偵丄偦偺攈惗揑宍懺偵偼惗嶻夁掱偑側偄偐傜丄忚梋壙抣偑惗嶻偝傟側偄偙偲偵側傞丅偡傞偲丄戞嶰師嶻嬈偐傜惗傒弌偝傟偰偄傞偍傃偨偩偟偄忚梋壙抣乮棙弫乯偼丄慡偰戞擇師嶻嬈偱惗嶻偝傟偨傕偺偱側偗傟偽側傜側偄丅
丂偙傟偼丄堷梡暥偺椺偵傛傟偽丄尰戙擔杮偺慡楯摥幰偺53亾傪愯傔傞戞嶰師嶻嬈廇嬈幰偼丄慡偔忚梋壙抣傪惗嶻偟偰偍傜偢丄慡偰偺忚梋壙抣乮棙弫乯偼丄34.9亾乮惓妋偵偼偦傟埲壓偺妱崌乯偺戞擇師嶻嬈廇嬈幰偵傛偭偰丄惗嶻偝傟偰偄傞偙偲傪堄枴偡傞偺偱偁傞丅
丂戞擇師嶻嬈偵偦傟傎偳棙弫偑弌傞偺偱偁傟偽丄帺桼嫞憟偵傛傞棙弫棪偺暯嬒壔偺尨懃偵傛偭偰丄戞擇師嶻嬈偺廇嬈幰偑偳傫偳傫憹偊傞孹岦偵偁偭偰偟偐傞傋偒偱偁傠偆丅尰幚偼慡偔媡偱偁傞丅偙偙偵婎杮柦戣噦俁偺嘆偺柕弬傪尒傞巚偄偑偡傞丅
丂忚梋壙抣偺惗嶻偵娭偡傞婎杮柦戣噦俁偼丄偦偺嘆媦傃偦偺嘇偺椉曽偲傕丄尰戙幮夛偵偼揔墳偟側偔側偭偰偄傞丅偙傟偼丄帒杮榑偵偍偄偰嵟廳梫僥乕儅偱偁傞乽忚梋壙抣榑乿偺攋嶻傪堄枴偡傞傕偺偱偁傞丅
丂
乮俀乯戞俀朄懃乮亖婎杮柦戣噦俉乯偺専摙
丂帒杮榑戞侾姫丒戞俀姫偱偼彜昳偼丄壙抣偡側傢偪偦偺惗嶻偵搳偠傜傟偨幮夛揑暯嬒揑拪徾楯摥偺戝偒偝偳偍傝偵幚尰偝傟傞偲偄偆偙偲偑慜採偝傟偰偄偨丅偟偐偟丄尰幚偺帒杮庡媊幮夛偵偍偄偰偼丄屄乆偺彜昳偼壙抣偳偍傝偵偱偼側偔丄惗嶻壙奿丄偡側傢偪僐僗僩乮旓梡壙奿乯僾儔僗暯嬒棙弫偱幚尰偝傟傞丅儅儖僋僗偼丄偙偺棟榑偵偮偄偰師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅
乽棙弫傪倫偲柤晅偗傟偽丄掕幃丂倂亖們亄倴亄倣亖倠亄倣丂偼掕幃丂倂亖倠亄倫丂偡側傢偪彜昳壙奿亖旓梡壙奿亄棙弫偵揮壔偡傞丅乿乮帒杮榑戞俁姫戞侾復丄p.46乯丂偦偟偰偦偺棟榑偐傜懕偗偰儅儖僋僗偼乽棙弫棪偺孹岦揑掅壓偺朄懃乿乮偙偙偱偄偆戞俀朄懃乯傪摫偒偩偟偨丅
丂偙偙偱偼丄偙偺戞俀朄懃偺専摙傪峴偆丅傑偢師偵帵偡俀偮偺岞幃偵拲栚偝傟偨偄丅
丂
丂丂丂彜昳偺壙抣 倂亖晄曄帒杮乮c乯亄壜曄帒杮乮v乯亄忚梋壙抣乮m乯乧乧乧乧乮俹乯
丂
丂丂丂棙弫棪 俹乫亖 忚梋壙抣 (m)丂乛乷晄曄帒杮 (c)亄壜曄帒杮 (v)乸乧乧乧乧乮俻乯
丂
丂 忋婰乮P乯丄乮Q乯偺岞幃偵偍偗傞壜曄帒杮乮v乯偼椉幰嫟偵惗嶻夁掱偵偍偗傞楯捓傪堄枴偡傞丅偙偺拞偵偼彨棃偺楯捓偲側傞傋偒惈幙偺傕偺偼娷傑傟偰偄側偄丅偟偐偟丄晄曄帒杮乮c乯偺応崌偼摨偠晄曄帒杮偱傕乮P乯幃偲乮Q乯幃偲偱偼偦偺撪梕偑堎側偭偰偄傞偺偱偁傞丅師偵偦偺堘偄傪帵偦偆丅
丂
乮P乯幃偺晄曄帒杮丗
丂丂乽傢傟傢傟偑丄壙抣惗嶻偺偨傔偵慜戄偟偝傟偨晄曄帒杮偲偄偆応崌偵偼丄偦傟偼丄慜屻偺娭楢偐傜斀懳偺偙偲偑柧傜偐偱側偄偐偓傝丄偄偮偱傕丄偨偩惗嶻拞偵徚旓偝傟偨惗嶻庤抜偺壙抣偩偗傪堄枴偟偰偄傞偺偱偁傞乿乮戞侾姫俹.227乯
丂
乮Q乯幃偺晄曄帒杮丗
丂丂乽棙弫棪偼丄惗嶻偝傟偰幚尰偝傟偨忚梋壙抣偺検傪丄彜昳偵嵞尰偡傞徚旓偝傟偨帒杮晹暘偩偗偱寁傞偙偲偵傛偭偰偱偼側偔丄偙偺帒杮晹暘丒僾儔僗丒徚旓偝傟側偄偑廩梡偝傟偰堷偒懕偒惗嶻偵栶棫偮帒杮晹暘偱寁傞偙偲偵傛偭偰丄寁嶼偝傟側偗傟偽側傜側偄乿乮戞俁姫俹.239乯偮傑傝丄
丂
丂丂 丂 乮俹乯幃偺晄曄帒杮乮c乯乧乧惗嶻夁掱偱偺懝栒暘
丂丂丂丂乮俻乯幃偺晄曄帒杮乮c乯乧乧惗嶻夁掱偱偺懝栒暘亄巆懚暘
丂
偲偄偆偙偲偱丄柧傜偐偵乮P乯幃偲乮Q乯幃偲偺晄曄帒杮偺撪梕偑堎側傞偺偱偁傞丅
丂
丂婎杮柦戣噦俉乽棙弫棪偺孹岦揑掅棊偺朄懃乿偼丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂 棙弫棪 俹乫亖丂 倣丂乛 俠丂丂丂丂丂乧乧乧乧丂乮A乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亖丂 倣乫倴 乛乮們亄倴乯丂 丂乧乧乧乧丂乮B乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亖丂 倣乫乛乮們乛倴亄侾乯丂 乧乧乧乧丂乮C乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
偲棙弫棪偺岞幃傪曄宍偟丄乮C乯幃偵婎杮柦戣噦俆乽帒杮庡媊揑拁愊偺堦斒朄懃乮晄曄帒杮偺憡懳揑憹戝偲壜曄帒杮偺憡懳揑尭彮乯乿傪揔梡偡傞偙偲偵傛偭偰徹柧偝傟偰偄偨丅
埲壓丄弴傪捛偭偰婎杮柦戣噦俉乮戞俀朄懃乯偺柕弬傪巜揈偟偰傒傛偆丅
丂
丂嘆丂婎杮柦戣噦俆乮晄曄帒杮偺憡懳揑憹戝偲壜曄帒杮偺憡懳揑尭彮乯偵偍偗傞晄曄帒杮偼丄乽徚旓偝傟傞惗嶻庤抜偺壙抣乿傪偝偟丄枹徚旓晹暘偺惗嶻庤抜偺壙抣偼娷傑傟側偄偙偲傪丄戞俀復偺乽婎杮柦戣噦俆偺夝愢乿偱妋擣偟偰偍偄偨丅偟偐傞偵丄崱尒偰偒偨傛偆偵丄棙弫棪偺岞幃偺晄曄帒杮偵偼丄枹徚旓晹暘偺惗嶻庤抜偺壙抣偑娷傑傟偰偄傞偨傔偵丄乮C乯幃偵婎杮柦戣噦俆傪揔梡偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄偙偺戞侾抜奒偱偼丄戞俀朄懃偑惉傝棫偮偐斲偐偼慡偔晄柧偱偁傞丅
丂
丂嘇丂偲偙傠偱丄乮Q乯幃偱偼側偵屘偵惗嶻夁掱偱偺懝栒暘偺懠偵巆懚暘傪傕娷傔偨偺偩傠偆偐丅偙偺巆懚晹暘偼丄夛寁棟榑偐傜尒傟偽柧傜偐偵戄庁懳徠昞偺帒嶻崁栚偱偁傝丄彨棃偵偍偄偰旓梡壔偡傞惈幙偺傕偺偱偁傞丅偦傟偼丄慜復偱徻偟偔弎傋偨捠傝丄摉婜偺旓梡乮懝塿寁嶼彂崁栚乯偲偼姰慡偵嬫暿偝傟側偗傟偽側傜側偄丄堎幙偺傕偺偱偁傞丅巆擮側偑傜棙弫棪偺岞幃偼丄帒嶻偲旓梡偲傪柧妋偵嬫暿偱偒偢丄崿摨偟偨傑傑嶌惉偝傟偰偄傞丅
偮傑傝丄晄曄帒杮偵偼丄旓梡偩偗偱側偔帒嶻傕娷傑傟偰偄傞偑丄壜曄帒杮偵偼帒嶻偑娷傑傟偰偍傜偢丄旓梡偩偗偱偁傞偲偄偆嬶崌偵丅旓梡偺悢抣偲帒嶻偺悢抣偲傪儈僢僋僗偟偰偺壛尭忔彍偼晄壜擻偱偁傞丅偦傟偼偁偨偐傕丄柺愊偺悢抣偲懱愊偺悢抣偲傪儈僢僋僗偟偰壛尭忔彍偡傞偙偲偑偱偒側偄偺偲摨條偱偁傞丅廬偭偰丄偙偺戞俀抜奒傑偱偔傞偲丄棙弫棪偺岞幃偼丄棟榑揑偵柕弬偟偨撪梕偺岞幃偱偁傞偙偲偑柧傜偐偵偝傟偨丅
丂
丂嘊丂彯丄偙傟偵愭棫偮慜愡乽戞侾朄懃乮亖婎杮柦戣噦俆乯偺専摙乿偱偼丄婎杮柦戣噦俁偲婎杮柦戣噦俆偲偑丄楌巎揑帠幚偐傜偄偢傟傕岆傝偱偁傞偙偲偑徹柧偝傟偰偄傞丅廬偭偰丄偙偺俀偮偺婎杮柦戣傪慜採偲偟偰惉傝棫偮婎杮柦戣噦俉傕丄幚偼丄婛偵慜愡偺抜奒偱攋嶼偟偰偄偨偲傕尵偊傛偆丅
丂婎杮柦戣噦俉乮戞俀朄懃乯偑丄偙偺傛偆側寢榑偵帄偭偨偲偄偆偙偲偼丄帒杮榑偵偲偭偰抳柦彎偱偁傞丅偙偺偙偲偼丄偡側傢偪丄儅儖僋僗偑梊尵偟偨楌巎揑夁掱傪宱偰偺丄帒杮庡媊幮夛偺乽嫟嶻庡媊傊偺昁慠惈偼側偐偭偨乿偙偲傪徹柧偡傞傕偺偱偁傞丅偙偙偵杮挊偺庡戣偼丄堦墳姰椆偟偨丅
丂
丂偝偰師偼丄僀僊儕僗偺摑寁偑帵偡傛偆偵壜曄帒杮乮恖審旓乯偺憡懳揑尭彮偐傜偱偼側偔丄媡偵恖審旓偺憡懳揑憹戝偐傜丄棙弫暘攝棪偑掅壓偟丄婇嬈偺丄偦偟偰帒杮庡媊幮夛偺懚懕偦偺傕偺偑婋婡偵昺偟偰偄傞偲偄偆帠偼拲栚偵抣偟傛偆丅偙偺帠幚偼丄儅儖僋僗偑梊尵偟偨楌巎揑抜奒傪宱偰偺丄嫟嶻庡媊傊偺昁慠惈偼側偄偑丄懠偺抜奒傪宱偰偺奧慠惈偼偁傞偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅傕偭偲傕丄帒杮庡媊丒嫟嶻庡媊傪栤傢偢丄楯摥幰偑奺恖偺楯摥埲忋偺捓嬥傪梫媮偟偨応崌偵偼丄崙壠慡懱偺宱嵪傕惉傝棫偨側偄偙偲偼摉慠偱偁傠偆丅
丂傕偟傕暯榓揑埥偄偼朶椡揑偵丄帒杮庡媊幮夛偐傜嫟嶻庡媊幮夛偵堏峴偟偨応崌丄幮夛偼偳偺傛偆偵曄傢偭偰偔傞偺偱偁傠偆偐丅師偺戞俀晹偱偼丄嫟嶻庡媊傊偺奧慠惈傪峫椂偟偰丄帒杮庡媊幮夛偲嫟嶻庡媊幮夛偲傪宱嵪揑懁柺偐傜斾妑偟偰傒傞丅