第6章 分配部門
(1)共産主義社会の第一段階における分配
共産主義社会における分配のあり方について、マルクスは「ゴータ網領批判」の中で、
①共産主義社会の第一段階における分配と、
②共産主義社会のより高度の段階における分配、
との二段階に分けて論じている。ここでもそれに従って論を進めたい。
まず共産主義社会の第一段階に於ける分配のあり方として、次のように述べている。
「資本主義社会からうまれおちたばかりの共産主義社会の第一段階においては、これらの生活資料は各人の提供した労働量に応じて分配される。この労働量は、労働時間に労働の強度を加味して測定される。このように生活資料を、各人の提供した労働量に応じて分配するとすれば、各人の能力が不平等であるかぎり、なお分配にたいする請求権も不平等となることをまぬがれない。
平等の権利とは不平等の労働にたいする不平等の権利である。こうした不平等は、共産主義社会の第一段階においては避けることのできないものである。この社会は長いうみの苦しみののち、やっと資本主義社会からうまれたばかりであって、労働の生産力はまだ十分に伸びていないからである。権利というものは、その社会の経済的装備、およびそれによって生じる文化の発達よりも高く登ることはできない。」
(マルクス・エンゲルス全集、第19巻P.19〜21趣旨)
そして、このような共産主義社会の第一段階においては、配分する前に次のようなものが控除されなければならないという。
「ところで、この社会的総生産物からは、次のものが控除されなければならない。
第一に、消耗された生産手段を置きかえるための補填分 ………①
第二に、生産を拡張するための追加部分 ………②
第三に、事故や天災による障害にそなえる予備積立または保険積立。 ………③
『労働の全収益』中からこれらのものを控除することは経済上の必要である。この控除の大きさは、もちあわせている手段と力とに応じて、また一部は確率計算によって決定されるべきものである。しかし、けっして正義によって算定できるものではない。総生産物の残りの部分は、消費手段としての使用にあてられる。しかし、各個人に分配されるまえに、このなかからまたつぎのものが控除される。
第一に、直接に生産に属さない一般管理費 ………④
この部分は最初から、今日の社会にくらべればきわめてひどく縮小され、そして新社会が発展するにつれてますます減少する。
第二に、学校や衛生設備等のような、欲求を共同でみたすためにあてる部分……⑤
この部分は最初から、今日の社会にくらべてひどくふえ、そして新社会が発展するにつれてますますふえる。
第三に、労働不能者等のための元本。つまり、今日のいわゆる公共の貧民救済費に当たる元本」(同上P.19) ………⑥
次に、以上の六項目を財務諸表と対比させてみたい。第1部で見てきたように理論上の剰余価値は、現実には利益として目に見える姿となって表れてくる。従って剰余価値の処分(分配)は、現実には利益の処分(分配)として表れてくる。資本論においてマルクスは、「剰余価値は全て資本家が搾取する」と前提しているが、実際にはどうであろうか。今日の日本で行われていることを、財務諸表の最終段階である利益処分計算書に見てみよう。
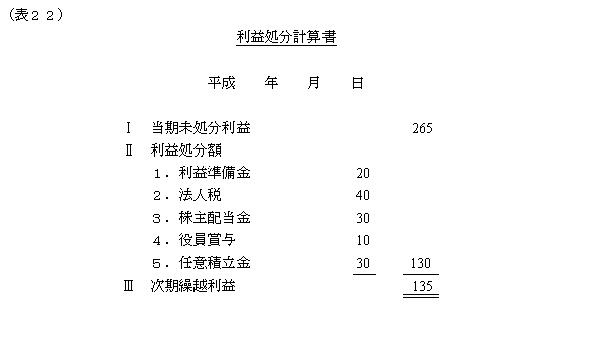
上の表は、利益処分計算書の一例である。現代の資本家をどのように定義するかによって、資本家の範囲は大分変わってくる。しかし、この利益処分計算書を一瞥しただけでも、「利益(剰余価値)の全てを資本家が搾取する」ということはあたらないであろう。更にこの利益処分計算書に損益計算書を連動させて、ゴータ網領批判の6項目とを対比すれば、現代資本主義社会の配分様式と、共産主義社会の第一段階における配分様式との比較がほぼ可能になるので、これを表示してみよう。
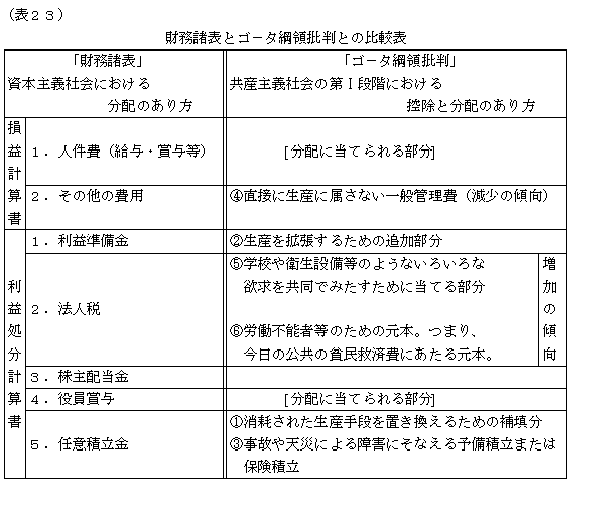
当然、財務諸表の各項目とゴータ網領批判の各項目とが厳密な意味で比較できるものではない。また、利益処分項目の検討をつうじて分配様式を考察する際には、貸借対照表の資本の部に表示される諸項目が、誰の持分を表すかといういわゆる会計主体論の問題をさけてとおることはできまい。しかし、会計理論の方だけ厳密にしても、対比される相手が厳密でなければあまり意味がない。今の段階では極めておおざっぱであり、不正確であることは十分承知の上で、両者の類似性を指摘しておきたいのである。
この表で明らかなように、共産主義社会で分配の前に控除されるべき部分は、今日でも実質的に控除されており、その残りの部分が分配にあてられている。即ち、
①消耗された生産手段を置き換えるための補填分、及び
③事故や天災による障害にそなえる予備積立または保険積立は「任意積立金」として控除され、
②生産を拡張するための追加部分は「利益準備金」として、
④直接に生産に属さない一般管理費は、損益計算書内の人件費以外の「一般管理費」として、最後に、
⑤学校や衛生設備等のような欲求を共同でみたすためにあてる部分、及び
⑥労働不能者等のための元本、つまり今日のいわゆる公共の貧民救済費にあたる元本は「法人税」としてそれぞれ控除されている。
従って、残された他の部分が分配に供せられるのであるが、それは財務諸表においては
(イ)損益計算書上の人件費(給与・賞与等)、
(ロ)利益処分計算書上の、役員賞与、株主配当金である。それに、ここで
(ハ)製造原価報告書上の労務費をも加えれば、共産主義社会における分配に相当する部分は全て含まれるであろう。
このうち、「株主配当金」だけは、共産主義社会にはないという意味で、特殊であるから次節で検討する。しかし、その他の控除及び分配は、共産主義社会の第一段階における分配も、現代資本主義社会における分配(控除も分配の一部と考える)も、極めて類似していると言えよう。
(2)株主配当金に関する一考察
財務諸表とゴータ網領批判との比較表の中で「株主配当金」だけが共産主義社会には、それに相当する分配がない。言い換えれば「株主配当金」以外は、現代資本主義社会と共産主義社会の第一段階における分配のあり方は、ほぼ同じである事がわかった。そこで、ここでは「株主配当金」に関して考察してみよう。この場合のポイントは、株主配当金を受け取る株主とは誰か、という問題である。
(①日本の場合)
「日本国勢図会」、1977〜97年度版(国勢社)によれば、所有者別持ち株比率の推移は下図の通りである。個人持ち株は1950年代の60%台から、45年後の1995年には23.6%にまでその比率が下がっている。
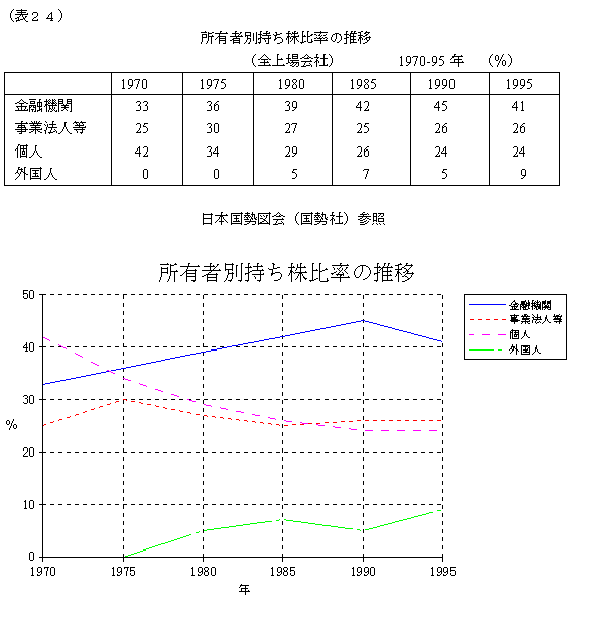
従って、およそ全体の4分の3を金融機関や事業法人等の法人が所有し、他の4分の1を個人が所有している。しかも、個人の持ち株比率は年々減少の傾向にある。株主の大半が法人であるということは、多くの株式が法人間で持ちつ持たれつ(株式の相互保有)の状態にあるということである。
全ての分配額に対する個人株主への配当金の比率はどの程度のものであろうか。例えば労務費・給与・役員賞与・株主配当金に対する分配額が次の通りであったと想定しよう。
労 務 費 390
給 与 100
役員 賞与 10
株主配当金 40
――――――――――――
分配額合計 540
この場合の個人株主への分配比率は、
40×1/4÷540≒1.9%(1/4は全株式に対する個人の持ち株比率を表す)
つまり、約1.9%に過ぎないことになる。更に控除も分配の一部と考えるならば、分配額合計はもっと大きくなるため、その比率は更に小さくなるであろう。
マルクスは、ゴ−タ網領批判の中で「共産主義社会の第一段階においても避けることのできない不平等として甘受しなければならない部分が存在する」と言っている。この株主配当金はその部分の比率と比べて、果たして大き過ぎるであろうか。「役員賞与」についても全く同様のことが言えるのであるが、役員賞与が他と比べて法外に高い場合は、「避けることのできない不平等として甘受出来なくなることは当然である。
尚、ここで「法人株主への配当額」について論及しなかったのは、それが再び企業の収益源となって法人に還流していくため、個人に対する分配の公平、不公平を論ずる場合には直接、影響しないと考えたからである。
(②アメリカの場合)
私は今ここに、P.F.ドラッカー著の「見えざる革命」(ダイヤモンド社)というショッキングなレポートを手にしている。その中で氏は、アメリカこそ真の社会主義国であるとして、その根拠を次のように述べている。
「社会主義を労働者による生産手段の所有と定義するならば、アメリカこそ史上初のかつ唯一の真の社会主義国というべきである。しかも、この定義こそ、社会主義の伝統的かつ唯一の厳格な定義である。今日アメリカの民間企業の被用者は、その私的年金基金を通じて、少なくとも全産業の株式の四分の一を所有する。彼らは、全産業を優に支配しうるだけの株式を手にしている。
さらに自営者、公務員、教職員の年金基金が、少なくとも全産業の株式の一割を所有する。したがって、アメリカの被用者と自営者は、全産業の株式の三分の一以上を所有していることになる。今後10年を考えると、年金基金はその株式所有をさらに伸ばし、1985年あるいはそれ以前において、全産業の発行株式の五割以上を所有することになるにちがいない。」(同P.2)
つまり、アメリカにおいては、被用者(労働者)こそが大株主になりつつあると言うのである。このように考察してくるならば、現代資本主義社会における「株主」は、100年前にマルクスが目撃した「資本家」とは大分その様相を異にしており、近い将来には更に、資本家とはかけ離れた実体となっていくであろうことが予想されるのである。
以上のことから、「株主配当金」の有無によって、現代資本主義社会と、共産主義社会の第一段階とが、決定的に異なる社会であると考える必要はない。むしろ、第(1)節でみたように、両者間には類似点が非常に多いことに、我々は注目すべきであろう。
(3)共産主義社会のより高度の段階における分配
続いて、共産主義社会のより高度な段階における分配について、マルクスは同じゴータ網領批判の中で次のように述べている。(全集P.21)
「共産主義社会のより高度の段階で、すなわち個人が分業に奴隷的に従属することがなくなり、それとともに精神労働と肉体労働との対立がなくなったのち、労働がたんに生活のための手段であるだけでなく、労働そのものが第一の生命欲求となったのち、個人の全面的な発展にともなって、またその生産力も増大し、協同的富のあらゆる泉がいっそう豊
かに湧きでるようになったのち――そのときはじめてブルジョア的権利の狭い限界を完全に踏みこえることができ、社会はその旗の上にこう書くことができる――各人はその能力におうじて、各人はその必要におうじて!」と。
共産主義社会のより高度の段階に至る条件が述べられているわけだが、この文章を分解して、一歩深く検討してみよう。
①個人が分業に奴隷的に従属することがなくなる。
②精神労働と肉体労働との対立がなくなる。
③労働が単に生活のための手段であるだけでなく、労働そのものが第一の生命欲求となる。
④個人の全面的な発展
⑤生産力の増大
⑥協同的富のあらゆる泉がいっそう豊かに湧きでるようになる。
以上のように分解した文章を整理しなおしてみると、①⑤⑥は、もっぱら、湧き出る程の生産力の増大を前提とし、②③④は、差別感、怠惰性、エゴのない完成された人間社会を前提としていることがわかるのである。従って、これを一言で言えば、
(Ⅰ)湧きでるほどの生産力の増大と
(Ⅱ)菩薩か仏の如く完成された人間の社会と。
以上の2大条件が整った場合に、
(Ⅰ)各人はその能力に応じて働き
(Ⅱ)各人はその必要に応じて分配される。
という共産主義社会の“より高度の段階”は実現すると言えよう。
しからば、この2大条件の実現の可能性や如何に。マルクス主義者は、共産主義社会にさえなれば、あとは時間の問題で、必ず実現されると考えているようであるが、私は、それ程甘くはないと考える。次にその理由を述べてみよう。
(条件Ⅰ)……「湧き出る程の生産力の増大」について
近年、世界的な問題として提起されつつある中に、資源の枯渇の問題がある。マルクスの時代は、生産力が低かったがために、民衆は貧乏を強いられた。しかし、生産力さえ増大すれば、自然的富は無限にあるのだから、民衆はいくらでも豊かになり得る、と考えていたようだ。この思想は、つい30年ほど前まで生きていたのであり、資源が枯渇するなどとは、誰も考えなかったことである。
現実は、どうやら自然的富は無限ではないようだ。生産力は絶えざる技術革新によって、おそらくマルクスの想像を絶する程の増大を示していると言ってよかろう。しかし、自然的富の限界という障害が、共産主義社会のより高度の段階を実現する前に大きく立ちはだかったのである。今や物質的富を追求する時代から、自然的富の再生産と調和を図りながら前進しなければならない時代に入ったのである。それを無視した場合、人類の未来は極めて見通しの暗いものとなってしまうであろう。
(条件Ⅱ)……「菩薩か仏の如く完成された人間の社会」について
これは単に条件文から読み取れるだけではない。その結果としての「各人はその能力に応じて働き、各人はその必要に応じて分配される」という文からも同じことが言えよう。即ち、「能力に応じて働き」とは、ある人は自分の生活に必要以上働くであろうし、またある人は、自分の生活に必要以下しか働かない。しかし、どちらの人にも、必要に応じて分配されるわけである。
この場合、後者の人に不服はあるまいが、前者の人に不満がないであろうか。自分の働いた分も他の人にあげようという気持ちは、なかなか持てないものである。その証拠に、共産主義者も、もとはと言えば、自分(労働者)の働いた分は、自分(労働者)がもらいたい。即ち、資本家に搾取されたくないから共産主義社会を目指すのだから。奉仕的精神が各人にあれば、少しぐらい資本家に搾取されたからといって、腹を立てたりはしないだろう。
人間生命の奥深くに巣食っている欲望や、エゴ、怠惰性などの汚れた生命は、資本主義社会から共産主義社会になったからと言って、自動的に浄化されるとは考えられまい。むしろ、もし人間の生命が美しく蘇生して、皆の生命が、菩薩の如き利他の精神や、仏の如く清浄な心で満たされてくるならば、資本主義であろうと、共産主義であろうと、富の分配について問題になるようなことはあるまい。
逆に、人間の生命が浄化されないならば、いつまでたっても共産主義社会のより高度の段階は実現しないことになる。実現の鍵は、人間の生命の問題に帰着して来る。資本主義か、共産主義かの問題よりも、より本源的には、人間生命の浄化が可能か否かの問題になって来るようである。
以上の通り、マルクスの言う「共産主義社会のより高度の段階」は、一方の資源の枯渇という外的要因から、そして他方の、人間の生命という内的要因から、その実現性は極めて低い。むしろ実現の可能性は無いと認識した方が良いであろう。科学的社会主義と言われ続けて来たマルクシズムも、結局、空想的社会主義でしかなかった事を、私はここに証明する結果になってしまったのである。その上で、我々人類はどのように生きるべきか。その道を模索しなければならない。私はその第一段階の手掛かりとして、E.Fシュマッハー著による「人間復興の経済」を推薦させていただきたい。